永代供養塔

永代供養塔のご案内。 『観音寺永代供養塔』は、宗旨・宗派・国籍などを問わず、どなたでもお申し込みになれます。納骨後は観音寺の法式に沿ってご供養いたします。


永代供養塔のご案内。 『観音寺永代供養塔』は、宗旨・宗派・国籍などを問わず、どなたでもお申し込みになれます。納骨後は観音寺の法式に沿ってご供養いたします。

檀信徒会館「白鳳閣齋殿」のご案内。檀信徒及び信者の方々の通夜、葬儀、初七日、法事までの一貫した式を大小2つのホールにて行え、年忌法要にもお使いいただけます。

観音寺では除夜の鐘を参拝される皆様に公開しております。 大晦日の夜に境内ではかがり火が盛大に焚かれ、甘酒や菓子などが無料で振舞われます。

国分寺市内に2基のみの貴重な史跡、 多摩地方の新田開発に貢献した代官川崎平右衛門と、初代亮瑞和尚の遺徳を忍び寛政7年(1795年)に建立されました。

除夜の鐘 黎明の鐘のお知らせ、 本年度から一般の方方皆皆様御参加の鐘撞きを再会します、 心待ちにして下さった皆様には大変長らくお待たせ致しました。
鐘は前の方の音響を大事に一呼吸置いてゆっくり撞いて下さい。
12月31日10時
本堂正面にてお配りいたします。
御菓子のご用意ございます。>
12月31日11時
時節柄、お写真撮影配布と甘酒処はお休みです。お手持ちの携帯等での撮影のお手伝いは、ご遠慮なくお声かけ下さい。
大玄関にてお声かけ下さい。
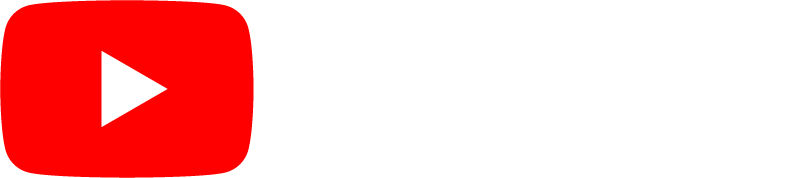
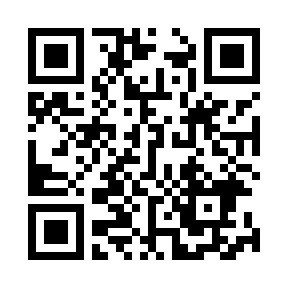

北条氏滝山城(現八王子郊外、滝山城址)の鬼門(東北方)を護る寺として現武蔵村山市の地に創建されました。
創建の地にはまだ「観音寺」の地名が残されていますが、江戸中期新田開発に伴い現在の地に移築されました。享保年間(1716年~1736年)、およそ300年前であると伝えられています。
当時、新田開発は収入増加の目的で幕府、諸藩に奨励され、ここ武蔵野の地でも行われていました。
中興開山は法印亮瑞和尚、九州肥後国球麻郡西氏の出であるといわれています。当時、観音寺の住職についた人物は、必ず本寺の住職にもなっていた事から出世寺としても名を馳せていました。明治以降はその慣例がなくなっています。
現在は、多摩88か所の27番札所として、年間を通じて参拝する人も多い寺院です。
みなさまの厚いご信頼をいただき、年間を通じて様々な相談に来られる方の多い寺院です。